晦日(みそか)
段々と冬の空気感となって来ましたね。ピンとした空気感が良いです。
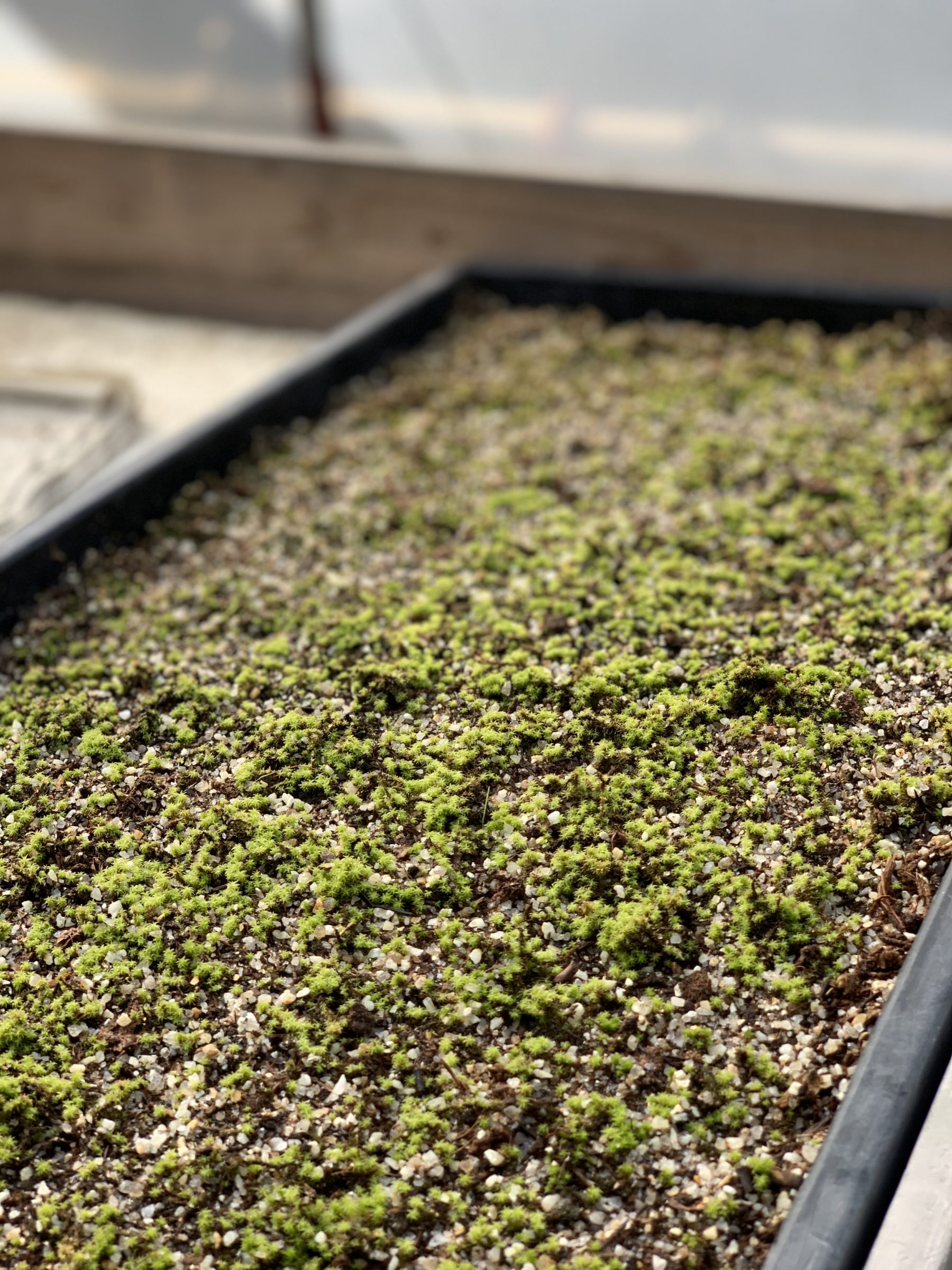
気が付くと、11月も最終日。
月末の最終日を晦日(みそか)と言い、年末つまり12月31日を大晦日と言いますね。
何かと忙しくなる時期ですが、あと1ヶ月頑張っていきましょう。
各現場や設計中の住宅は、どんどんと進んでいます。
コロナの影響もあり、何が起こるか分からない時代。
後回しにせずに、丁寧に進めるところはどんどんと取り組んでいきたいと思います。
藤原昌彦
段々と冬の空気感となって来ましたね。ピンとした空気感が良いです。
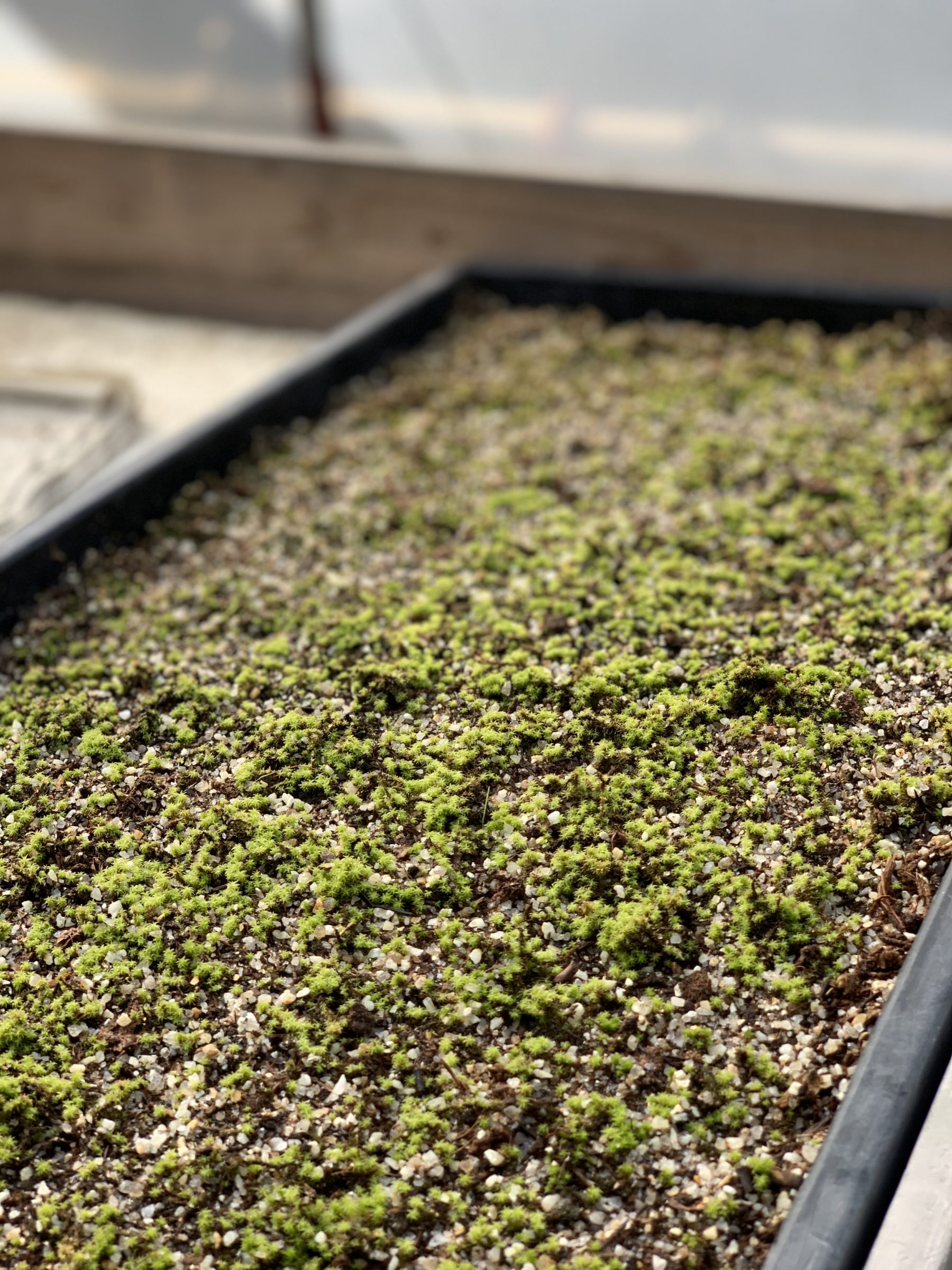
気が付くと、11月も最終日。
月末の最終日を晦日(みそか)と言い、年末つまり12月31日を大晦日と言いますね。
何かと忙しくなる時期ですが、あと1ヶ月頑張っていきましょう。
各現場や設計中の住宅は、どんどんと進んでいます。
コロナの影響もあり、何が起こるか分からない時代。
後回しにせずに、丁寧に進めるところはどんどんと取り組んでいきたいと思います。
藤原昌彦
一気に寒くなりましたね。急に寒くなったので、体がついて行かない感じになりそうです。

かねてより設計を行なっていました、倉敷市真備町に建築中の「真備町の家Ⅲ」。
本日、上棟を致しました。
平屋建てとしては一番大きく、敷地と建物のバランスを考えて計画した住宅です。
平屋建て+二世帯住宅。そして、世帯間の距離を生み出す「中庭」。
外から見ると、約80坪ぐらいに見えるかと思います。
全体の躯体が建ち上がり、建築の姿が見えてきました。
今回は、広さもあるため構造躯体の体力を負担する部分が仕上げとして見えてきます。
上棟の際には、傷がつかない様に注意を払いながら大工さんが組み上げていきました。
完成までは、まだまだ時間がかかりますが、楽しみです。
藤原昌彦
朝晩は冷え込みますが、日中は暖かいですね。

本日は、岡山市南区に建築中の「山田の家」にて、ダイニングチェアー・ソファーの打ち合わせを行いました。
現場は、上棟してから約1ヶ月が過ぎ大工工事の中盤あたり、年内には内部の大工工事が終わる予定です。
このタイミングで、山田の家に置くダイニングチェアー・ソファーの打ち合わせを現場を見ながら行いました。
何となくこの辺りから見える景色や、ダイニングの配置を確認。
あとは、ソファーの生地などをサンプルを取り寄せて見て頂きます。
午後からは、建築相談会を行いました。
これからのスケジュールのことや、予算の組み方、土地の探し方など多岐にわたり、約1時間30分ほどお話を交えながらさせて頂きました。
どんな物事においてもそうですが、事前の相談は早いほうがいろいろな物事が見えてきて良いですね。
藤原昌彦
少し寒くなってきたので、先日より薪ストーブに火を入れました。

薪ストーブは、直接的な火の暖かさだけではなく、輻射熱により暖かを感じることが出来ます。
薪ストーブ本体からの熱と煙突に上がる煙による熱で、建物の壁や天井・床が暖められ人体へと伝わっていきます。
身体の芯から暖かくなるので、本当に良い暖房器具です。
もう一つ良い点は、炎を眺められる事。
炎の揺らめきは、一定ではなく、ゆらゆらと見ていても惹かれます。
ご存じの方も多いかと思いますが、木々が揺れたり、炎の揺らめきなどは1/fゆらぎというリズムがあるそうです。(リズムという方言が正しいかどうかわかりませんが。。。)
自然界にある揺れが、心地よさを感じさせ、人を和ませる。
このデジタル時代だからこそ、大切にしたい自然の力。
自然と共に、いや自然界に間借りをしている人間だからこそ、大切にしていかなければならないと思います。
藤原昌彦
まだまだ日中は過ごしやすい気温ですね。コロナの影響はどこまで続くのか先が見通せない状況が続いています。

住宅を検討されている方々にとって、色々と大切な想いがあると思います。
住宅は、いくらでつくれますかと質問いただく事があります。
予算に収まるかどうか心配されての事だと思います。
心配になるのは当然のことであると思います。
実は、下限があるにしても予算はいくらでも良い気がします。
しかし、その予算と求められている要望・希望・想いが合致しているかどうか大切です。
できる限り予算に収まる様に、提案として生活様式の見直しや新しい暮らしかたや大切にしないといけないことなど、考えぬき創り上げていくことはできると思っています。
住宅は、クライアント様の価値を反映するものだと思います。
目の前の数値やモノを見ずに、もっと先の暮らしを考えながら設計できればと思います。
藤原昌彦
寒くなるかと思えば、暖かい一日でしたね。

住宅を設計する際の要望で、使い勝手の良いであるとか掃除がしやすいとか、つまり負荷のない、ストレスのない様にと要望される。
確かに、正しいことであり、設計の際には十分配慮しながら設計を行っている。
この負荷のないことを考えたとき、人の成長は止まるのではないかと思ってしまいます。
過剰な負荷は、人を傷つけることにはなるが、ある程度の負荷がなければ人の潜在能力は衰退するのではないかと思います。
多少の不便を楽しむことが、このコロナ後の時代に求められていく一つの暮らし方ではないかと。
暮らしを楽しむというのは、不便を楽しむことにもつながるのではないかと思います。
藤原昌彦
昨日は祝日で、お休みだったのですが、個人的にお世話になっているセレクトショップの「bevros womens」さんでクリスマスリースのワークショップに参加してきました。


もみの木を巻き付けるところから始まり、デコレーションをしていきました。
先生とおしゃべりしながら楽しく作れました~!!

早速、アトリエの玄関に飾りましたよ!!
直径50cmくらいあるのでとってもボリュームがあって綺麗です(^^)/
コロナの感染者の数が増えていますね。この先の見通しも中々難しいです。

お陰様で、アトリエにお越し頂いたり、メールにてお問い合わせ頂いたりしております。
住宅に求めるものは、その家族や人により様々。
私のところへ来る多くの方々が豊かな暮らしを求めて来られている気がします。
その中、よくある問い合わせで、耐震等級は幾つですがや、外皮性能は?、気密性のは?その他・・・。
これらは、確かに数字で分かってきますので、比較検討しやすいのだろうと思います。
簡単に数値で、お伝えすることができますが、この数字に合わせ行ったことが大切でそれを聞かないで数値だけが独り歩きするため、お逢いしてお話をさせて頂く際にお話をしています。
耐震性は当たり前の話で住宅性能表示等級3(建築基準法上の耐震等級3ではありません)を必ず許容応力度の構造計算にて取得しています。
断熱性能や気性能・冷暖房の計画は、クライアント様の予算によってきますので、各住宅とも違いが出ます。つまり、断熱性能や気密性能・冷暖房については、高い性能を出そうとすればコストと比例します。
比較したいのは、よくわかりますが住宅はそれだけでは成り立ちません。
公道ではレーシングカーが走れない様に、スペックがいくら良くても、豊かな暮らしはおくれないのです。
独りよがりの住宅ではなく、美しく後世に伝え続けられるような、暮らしを残していければと思います。
藤原昌彦
三連休の中日。天気が良く、行楽に行きたい感じですね。

定期的に建築の勉強会をしている仲間の大工さんの仕事を見せて頂きました。
石場建て建築。木造の伝統構法を言った方が伝わりやすいかもしれません。
使用する木材の選定から、墨付け木材の刻み(加工)を現代の工場などのプレカットでなく大工さん自身が行い組んでいく。
現代であれば、木と木が組み合わさる部分は、金物により接合させますが、伝統構法では木の組み合わせのみ。
この伝統構法は、簡単に言うと免震構造となります。
いろいろな接合部が柔軟に対応することにより揺れを吸収し、基礎に緊結せずにおいてあることで、揺れた際にズレることで建物の倒壊を防ぐ様になっています。
無形文化財登録の対象にもなっている伝統構法を行う大工の技術。
どうにか繋いでいきたい、技術の一つで無くしてはならない建築の文化ではないでしょうか。
藤原昌彦
いよいよ上棟向けて、大工さん登場です。

まずは、土台を敷くための墨出しをしてくれています。
二世帯住宅で平屋なので、面積が大きいので、土台敷きの前に準備を始めてくれています。
次は構造材の搬入など、現場は賑やかになっていきます。